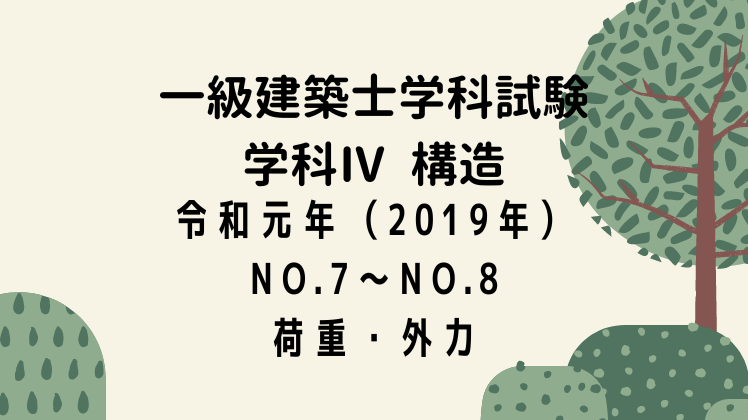
荷重・外力についてです。今回は、あまり難しい問題ではなかったかもしれません。
風荷重について分からない点があれば下記のブログも参考にしてください^^
・「平均風速の高さ方向を表す係数Er 、ガスト影響係数G」と「地表面粗度区分」の関係って?
〔No. 7 〕建築基準法における建築物の構造計算に用いる風圧力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 .風圧力の計算に用いる速度圧qは、その地方について定められている基準風速V0の2 乗に比例する。
2 .基準風速V0は、稀に発生する暴風時の地上10 mにおける10 分間平均風速に相当する値である。
3 .ガスト影響係数Gfは、「平坦で障害物がない区域」より「都市化が著しい区域」のほうが大きい。
4 .風圧力は、一般に、「外装材に用いる場合」より「構造骨組に用いる場合」のほうが大きい。
1 .風圧力の計算に用いる速度圧qは、その地方について定められている基準風速V0の2 乗に比例する。
答は○
速度圧qを求める式は、q=0.6×E×V02なので、基準風速V0の2 乗に比例します。
2 .基準風速V0は、稀に発生する暴風時の地上10 mにおける10 分間平均風速に相当する値である。
答は○
これはその通りです。基準風速V0は、稀に発生する中程度の暴風時を想定した10分間の平均風速です。
3 .ガスト影響係数Gfは、「平坦で障害物がない区域」より「都市化が著しい区域」のほうが大きい。
答は○
ガスト影響係数Gfとは、「最大瞬間風速/平均風速」を表したものです。基準風速V0は「平均風速」なので、突風が吹いたりすると基準風速よりも大きい風荷重が作用することもあることから、最大の速度圧(風圧力)の場合を考慮した係数のことです。
「平坦で障害物がない区域」と「都市化が著しい区域」(地表面粗度区分の違いのことですよ!!)のどちらが大きくなるかについては、「都市化が著しい区域」の方が大きくなります。新宿などの高層ビル群を思い出してもらうとイメージしやすいのですが、高層ビルの間にいるとビル風で強い風が吹くと思います。そういった事象を考慮して決められています。
4 .風圧力は、一般に、「外装材に用いる場合」より「構造骨組に用いる場合」のほうが大きい。
答は×
構造骨組用の風荷重は、架構全体に均した風荷重なのに対して、屋根吹き材等の風荷重は、局部的に大きな風荷重が作用するので、構造骨組用の風荷重よりも大きな風荷重となります。
〔No. 8 〕建築基準法における荷重及び外力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 .多雪区域以外の区域において、積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、積雪量1 cm当たり20 N/m2以上とする。
2 .店舗の売場に連絡する廊下の床の構造計算に用いる積載荷重は、建築物の実況に応じて計算しない場合、店舗の売場の床の積載荷重を用いることができる。
3 .建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、一般に、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に水平震度を乗じて計算する。
4 .建築物の固有周期が長い場合や地震地域係数Z が小さい場合には、地震層せん断力係数Ciは、標準せん断力係数Coより小さくなる場合がある。
1 .多雪区域以外の区域において、積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、積雪量1 cm当たり20 N/m2以上とする。
答は○
これは、設問の通りです。
積雪荷重=積雪単位荷重(N/m2/cm)×鉛直積雪量(cm)
・積雪単位荷重(N/m2/cm):雪の深さ1cmあたりの重さで、積雪量1 cm当たり20 N/m2以上とします。
・鉛直積雪量(cm):雪の積もった深さ。一般地域では30cmですが、多雪地域では各特定行政庁によって指定されます。
2 .店舗の売場に連絡する廊下の床の構造計算に用いる積載荷重は、建築物の実況に応じて計算しない場合、店舗の売場の床の積載荷重を用いることができる。
答は×
廊下の床の積載荷重について、「教室、百貨店・店舗、集会室」に隣接する場合の廊下は「集会室(その他)」の積載荷重とします。
廊下で一度に大人数がまとまって移動することを想定して、「集会室(その他)」(セミナー会場など大勢の人が集まっている状態)と同等であるとしています。
(積載荷重の大きさとしては、店舗の売場<集会室(その他)となります。)
3 .建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、一般に、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に水平震度を乗じて計算する。
答は○
地震力というのは、P=K×W(P:地震力、K:水平深度、W:重量)で表されます。地下部分の地震力についても同じように、
Qi=Q1+Σki×Wi
と表されます。Q1は1階の層せん断力、ki:地下の水平深度、Wi:地下部分の重量(=固定荷重と積載荷重との和)です。
すなわち、Q1:1階の層せん断力が「地上部分の地震力」、Σki×Wiが「地下部分の地震力」と理解して頂ければ大丈夫です。
4 .建築物の固有周期が長い場合や地震地域係数Z が小さい場合には、地震層せん断力係数Ciは、標準せん断力係数Coより小さくなる場合がある。
答は○
ここでは、建物の固有周期が長くなると振動特性係数Rtは小さくなります。(建物の固有周期が長い⇒ゆっくり揺れる⇒地震力が小さくなるというイメージをして頂ければと思います。)
また、地震地域係数Zは、1.0を基準とした地域による地震の発生頻度に応じた低減係数です。